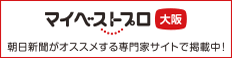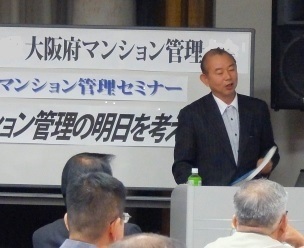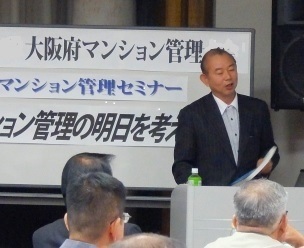マンション管理での『お悩み』ごとなら川口マンション管理士事務所にお任せください。
無料相談開催中。土日祝可
10時~20時まで(事前予約制)
ZOOM対応可能です
06-7878-6865
営業時間 | 9:00~17:00 |
|---|
過去のニュース
民泊関連ニュース NO3
最近、都心部(大阪市・神戸市・京都市)のマンションでは、民泊に対する懸念を持つ管理組合が多く、「民泊 管理規約改定」を含め、対策が急務となっています。マンション管理士としても留意しておりす。ここでは民泊関係のニュースをご紹介致します。貴管理組合の情報収集にお役立てください。
条例で「不可」対応も可能。民泊検討会 住居専用地域でも実施へ
規約上の「住宅」とは別概念
厚生労働省と観光庁は、5月23日、民泊サービスの在り方に関する検討会の第11回会合を開いた。制度設計骨子案で一定の要件内の民泊であれば「住宅」とみなし、住居専用地域でも実施可能と提示。ただ、条例等で不可の対応も可能としている。
旅館業法とは異なる新たな枠組みの民泊を「住宅を活用した宿泊サービスの提供」と位置付け、利用者に1日単位で貸し出すことを認める。
一定の要件は、規制改革会議4次答申の「年間提供日数180日以下」が報告されたが、検討会では引き続き検討する。1泊2日換算では90泊。
新たな枠組みは新法での実施を想定。住宅提供者は家主居住型・家主不在型共に行政庁への届け出を義務付け、無届け民泊実施者は罰則対象とする。提供住宅であることが分かる標識も掲示させる。管理規約違反の不存在確認は家主居住型では提供者本人、家主不在型では管理者が行う。管理者と仲介業者は登録制とする。
用途規制では、前回の会合で国土交通省の香山幹市街地建築課長は「家主共住型では実際に家主が居住しており、家主不在型でも日数制限等のより住宅としての基本的性格は失っていない。住宅に類似または住宅の概念に含まれるのではないか」との見解を示した。この考え方を踏まえ一定要件内の民泊は住居専用地域でも可としつつ、地域の事情に応じ条例で異なる対応も可としている。
香山課長は前回、マンションについて「個々の管理規約上の住宅が何を指すかは管理組合しか決められない」とも述べ、新制度にかかわらず各管理組合は規約で民泊の寡婦を明文化することが出来る点を強調している。
(マンション管理新聞 第1006号20160525より)
「家主不在型」は管理者が実施 4/22民泊検討会 管理規約の確認作業
厚生労働省と観光庁は4月22日、民泊サービスの在り方に関する検討会の第9回会合を開き、民泊サービスの制度設計案を示した。既存住宅を対象とするが新たな民泊サービスの性質を住宅または宿泊施設とみなす判断の仕方はまだ明示していない。
制度設計案の対象は旅館業法とは異なる枠組みで行う、「一定の要件を満たす」民泊。家主の居住の有無に関らず、既存住宅の活用を前提としている。住宅を提供する「民泊サービス提供者」には宿泊者の安全性確保や近隣住民トラブル防止など適正な管理を求め、届出制など行政が提供者を把握できる仕組みとする。
家主不在型は管理の業務を管理者に委託し、管理者は登録制とする。管理業務では利用者名簿の作成・備え付け、利用者に対する注意事項の説明、苦情の受け付け、当該住戸の法令、契約違反不在者確認を例示。管理規約との確認作業は管理者が行う形だ。宿泊者に民泊施設を紹介する仲介事業者も登録制とする。取り引き条件の説明義務、民泊サービスとしてのサイト上の表示義務、行政への情報提供義務を課す予定。違反者には業務停止命令や名称公表ができるようにする。
一定の要件に関する具体的な検討は次回以降。今回はこれまでの意見集約として営業日数は年30日以内、宿泊人数は1日4人以内、マンションでの管理組合の承認等が示された。会合後の記者会見で西海重和観光庁産業課長は「一定の要件が固まらないと、住宅か宿泊施設かの判断はできない」と説明した。(マンション管理新聞 第1004号20160425より)
管理規約の写しを確認 「民泊」解禁 指導要領書策定 兵庫県
兵庫県は簡易宿所「民泊」が4月から緩和されたのを受けて、指導要綱を策定する。5月1日から施工する予定だ。分譲マンションの管理規約については、厚生労働省が3月30日付で都道府県知事等に許可の際に確認を求める通知を行っている。同県生活衛生課によれば、通知に沿う形で指導要綱に盛り込む予定で、確認方法は、「規約の写しを付けてもらおうかと考えている」という。専有部分の用途について、「専ら住宅として使用」という一般的な居住専用の規定がある分譲マンションでは「それ以外は使ったら駄目だという認識でいる」としている。旅館業法を行うに当って、事前に管理組合等に説明会を開くことも求めるという。廃棄物の処理方法の掲示や設置等も定める予定だ。
同課は「住民に周知されないことでトラブルに発展することを防ぐ狙いがある。周知する中で、管理規約の確認をしてもらわないといけない」と話している。(マンション管理新聞 第1003号20160415より)
来年3月以降「禁止」で和解 シェアハウス使用差し止め
間仕切り撤去を猶予 東京地裁 複数の使用契約結ばず
都内の管理組合が法人区分所有者にシェアハウスの使用差し止めを求めていた訴訟の控訴審で、2月25日、和解が成立していたことが分かった。一審判決はシュアハウスの間仕切り撤去を命じる一方で生活共同体としての使用は認めていたが、和解で管理組合は各間仕切りの撤去を来年2月まで猶予し、法人区分所有者は同年3月以降、複数の使用契約締結を行わないことで決着した。
管理規約で住宅専用使用と規定しているマンションの1住戸(約44㎡)で、区分所有者が間仕切りを設け10区画に改装。7人程度が個別に被告法人と賃貸借契約を結び住んでいたとされる。昨年9月18日の東京地裁判決(谷口園惠裁判長)は、窓もなく2畳程度のスペースでの寝起きという使用態様は「住宅」に当たらないとして間仕切り全部の撤去を命じた。一方、契約の重複や1契約3人を超える使用であっても「入居者らが1つの生活共同体とし継続的に同居生活を営む関係にあり、その者らの生活の本拠として使用される限り」は規約違反の使用態様に当たるとはいえない、との判断を示した。結果的に間仕切りを撤去しても、ルームシェア同意の入居者であれば使用可能な形となり、被告法人は控訴し、原告組合は付帯控訴した。今回の和解では、法人側は来年2月までに間仕切りを撤去し、3月1日から複数の使用契約(賃貸借契約等を含む)を締結せず、1使用契約で3人を超える者に使用させず、使用者全員の氏名・連絡先を組合に通知する。ただし、使用者らが1つの生活共同体として継続的に同居生活を営む関係にあり、その者らの本拠として使用される場合を除く、との規定も設けた。1住戸に数部屋程度あり、トイレ・浴室・台所を共同とし、生活の本拠として同居生活をする場合、住宅専用規定の規約でも使用は容認されるということのようだ。
(マンション管理新聞 第1002号20160405より)
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
06-7878-6865
受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
メールアドレス :info@mankan1.com